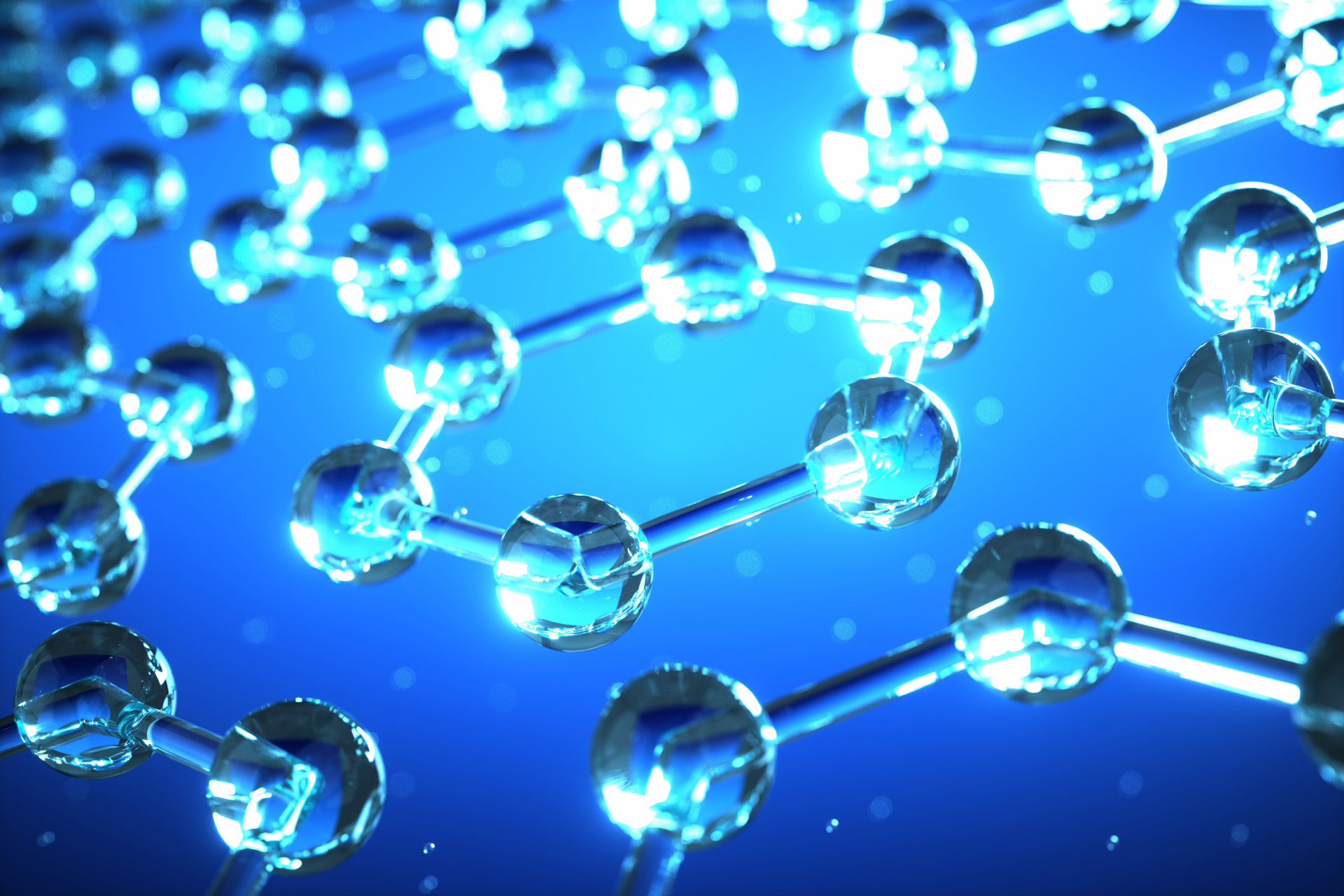前回は「目標を立てたほうが良い」という話を記事にした。

前回は1年間の目標の話であったが、
今回はとりわけ長期的なものである、
人生の目標はどのようにして立てるのかって話を書こうと思う。
著者の「人生における目標」
あなたには、人生の目標っていうのはあるだろうか。
学生であれば、「銀行員になりたい」とか「政治家になりたい」とか。
社会人であれば、「副社長の座に就きたい」とか「結婚して幸せな家庭を築く」とか。
もちろんなりたいものは人それぞれだからいいのだけど、著者の考える「目標」というのは違う。
ここで著者の人生における目標を言っておこう。それは・・・
世界中の子供に科学(化学)教育を施し、少しでも世界平和に貢献することだ!
・・・笑った人や、「は?」、って思った人もいるであろう。結構結構。
世界には、教育を受けられない子どもたちが6,100万人いると言われており、その半数以上がアフリカのサハラ砂漠より南の地域で暮らしています(出典:UNICEF2017)。学校が近くになかったり、あったとしても先生がいなかったり、様々な理由で教育の機会が奪われています。また、家計が苦しいために、保護者が子どもの勉強より労働を優先させてしまい、家事や水汲みなどで学校に行かせてもらえないこともあります。ほかにも、女の子であることを理由に教育を受けることが許されなかったり、紛争や災害によって教育の機会が奪われている子どもたちがいます。

著者は、化学講師として経験を積んだ後、稼げるようになったら海外で教鞭をとろうと考えている。
幸い、IT技術は後進国でも結構進んできており、人が海外に行かなくても、ネット回線を使えば世界中の人に教えることができるであろう。
著者がお金持ちになれば、
IT技術が進んでいない土地
(具体的には途上国と呼ばれている所の都市部からさらに遠隔地となっているような場所)
に出向いて理科の出張授業をしたり、
映像授業が見られるような施設を作っていきたいと考えている。

今したいと思っていることは・・・
① 化学講師として大成する。
② 法を侵さずに、モラルをもって、あらゆる手段でお金を稼ぐ。
③ 化学のみならず、理科教育に対してプロフェッショナルとなる。
④ 英語で授業ができるようになる。
ボーっと生きている場合ではない。
著者は心からこの目標を達成したいと考えている。
このブログも自分の人生の目標達成の手段として、やりたいことの一つだ。
忘備録にもなるし、収益化できたらお金を稼ぐこともできる。
息子がまだ小さいので、養育費や生活費もかかるであろう。
家族との時間も大切にしていきたいので、目標の達成は相当先になるだろう。
ただ、今のままの自分では決して叶えられない目標であるから、
日々自分をアップデートして、一歩一歩、前進していこうと思う。
「人生の目標」を立てるということ
著者が思う人生の目標の設定であるが、それは、
心の底からやりたいことで
2. 今のままの自分では到底できそうにないこと
にすれば良い。
冒頭の「銀行員」とか「副社長」というのは、現状の自分では絶対に叶えられないというものであればいいと思う。
しかし、現状の自分でなれる見込みがあるのならその目標は辞めておいたほうが良い。
なぜ、「今の自分では到底できそうにないこと」にするのか。
それは、自分を成長させるためである。
もし今の自分でできることを目標にしてしまったら、成長すること無く達成してしまうことになる。
人間の脳は「現状維持」を好む。本能によるものだ。
高校生物でいう「恒常性」、ホメオスタシスみたいなもの。
(自然界も変化を嫌う。レンツの法則だとか、ル・シャトリエの法則とかがそう。)
なぜこんな本能があるのかといったら、リスク回避だ。
せっかく同じ生き方をしていたら命の危険もなく平和に過ごせているのに、何か変化が起こったらひょっとすると生命の危機となることが起こるかもしれない。
その確率を下げるために、「現状維持」装置が脳に備わっているのだ。

Image by Gerd Altmann from Pixabay
何か新しいこと(ブログとか、部活とか、習い事とか)を始めたときに、
「もーやりたくねーーー!!!」
ってなるのもこの本能によるものだ。
なので、意図的にこの本能に抗う必要がある。
それがこの「人生の目標」設定の意図だ。
日々同じ生活の繰り返し、
そのサイクルの中には、「目標を達成するための行動」は入って無いはずだ。
なぜなら「現状の自分」には無いものだから。
そこで先程のような目標設定をしてみよう。
現状の自分ではないところに目標をおいているから、目標に近づくために情報収集やスキルアップをしようと行動するようになるだろう。
そうなれば昨日までの自分とは、違う自分になるはず。
しかし、ここで「現状維持装置」が働く。
意識していなければ、その装置の働きのまま、
「新しいことをしない、やーめた。」という選択肢になってしまうが、
そうすることで、目標達成のための行動込みの生活が現状となり、
今度は以前の自分が現状の外になり始めて、現状維持装置は働かなくなってくる。(新しいサイクルが現状となるからだ。)
これを繰り返して、目標に近づいていくのだ。
「現状維持装置に抵抗する」と言ったが、これができる理由は
上の囲みの1、本当に自分がやりたいことを設定しているからである。
この考え方の出処は苫米地英人氏のコーチング理論
理科教育の調べ物をしているときに、YouTube で偶然以下の動画に出会った。
この動画を見てから、いろいろ苫米地英人氏の動画を見ていった。
この方はオウム真理教事件の信者の洗脳を解いたなどの実績がある、機能脳科学者。
(これが一番有名なだけで、実績は他にも沢山ある。肩書もたくさん。)
著者がなるほどなと思うこともたくさんあり、セミナーなども行こうかと思ったが料金がかなり高額で諦めた。
苫米地英人氏はコーチング理論の元となる TPIE をルー・タイス氏と共に開発した人である。
TPIEとは?
ルー・タイスが確立したコーチングのコンセプトは、40年にわたって数多くの科学者による
検証、助言が重ねられ、常に進歩を続けてまいりました。
この度、基幹プログラムであるIIEは、苫米地英人による機能脳科学ならびに認知心理学の
最新の理論を応用し、より洗練されたプログラムとして再構築されました。
このプログラムが、世界トップレベルの成功のためのプログラムTPIEです。
TPIEプログラムの骨子
The Pacific Institute の理念「人は成長、変化、創造性において無限の可能性を持ち、
時代のどのような変化にも順応できる」に基づき、人間のマインドの働きと
行動の関係性を学び、成功へ向かう思考と行動を身につけていきます。最新の機能脳科学と認知心理学、社会的学習論、成功者研究による科学的な理論と、
40年にわたる研究の成果を活用した実践的な学習を21ユニットに分割して行います。日常の生活に組み込むことができるよう工夫された方法により、プログラム学習後、
身につけた思考と行動を即座に自身の習慣として取り入れることが可能となります。
生き方について色々ためになることがあるので、ぜひ youtube などで苫米地英人氏の動画を見てみると良い。
うさんくさいように思うけど、自分がなるほどと思う所は吸収してみよう。